
ある日突然、自分や家族・知人が、警察や検察庁による捜査、国税局や証券取引等監視委員会による調査の対象とされたり、逮捕、勾留されたら(留置場や拘置所に入れられること)どうしたらよいでしょうか。捜査の結果、犯罪が成立すると判断され、起訴されて裁判が始まったらどうしたらよいでしょうか。
逆に犯罪の被害に遭ったのに、警察に相談に行っても捜査をしてもらえない、という場合にはどうしたらよいでしょうか。
頼れるのは専門家の弁護士だけです。しかし、弁護士といっても刑事事件をほとんど担当したことのない人や、経験があっても捜査や裁判に関する十分な知識や能力のない人もいるので、注意が必要です。
そこで、刑事事件の流れと弁護士の役割を説明し、弁護士選びのポイントを解説いたします。
刑事事件の流れと弁護士の役割
ここではまず、刑事事件の一般的な流れと各場面で行われる弁護士の活動について説明します。分かりやすいように、①捜査・調査の始まり、②捜査・調査の実情、③事件の処理、④第一審の裁判手続、⑤控訴審(高等裁判所)・上告審(最高裁判所)の各段階に分けて、順番に説明していきます。
捜査・調査の始まり
捜査・調査を行う機関
捜査機関としては、警察官(警察署)、検察官・検察事務官(検察庁)等があり、検察官には、検事と副検事がいます。窃盗などの簡易な事件を取り扱うのが副検事です。調査機関としては、国税査察官(国税局、いわゆるマルサ)、証券取引等監視委員会職員(日本版SEC)、公正取引委員会職員(公取)等があります。
捜査機関(警察官、検事等)には逮捕・勾留といった身柄を拘束する権限や捜索差押え(いわゆるガサ)をする権限がありますが、調査機関(マルサ、SEC等)には、逮捕権限はなく、捜索差押えをする権限が与えられています。マルサが「否認すると逮捕するぞ」といったらそれは嘘で、脅しです。
捜査・調査の端緒(きっかけ)
捜査機関は、被害届・告訴・告発・職務質問・他の事件の捜査・報道・変死体の発見などから端緒を得て(被害届や死体の発見などをきっかけに)捜査を開始します。調査機関は、税務調査、証券取引のモニター監視等のほか密告、報道などからも端緒を得て(税務署の調査や日々の株取引の監視などをきっかけに)調査を開始します。捜査と調査の中身はほとんど同じです。
事件の受理
検察官は、通常、警察や国税局などから事件を受理(いわゆる送検や告発を受けること)してから捜査を開始します。警察から事件の送致を受けたり、調査機関から事件の告発を受けて捜査を始めるのが通常ですが、特捜部等は、自ら犯罪を探し出して捜査を開始したり、警察等を経由しないで直接、告訴・告発を受けて捜査を開始することもあります。
この段階の弁護士の役割
告訴・告発の手続きを行います。
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の人が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のことです。告発とは、告訴権者以外の人(第三者)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことです。
弁護士は、依頼者から事情を聞き、証拠資料を集めるなどして適正な告訴状・告発状を作成し、警察官や検事に提出します。きちんとした内容とそれに見合う証拠資料を付けた告訴状等を作成することは、専門性を要する仕事ですし、素人が作ったいい加減な告訴状等はなかなか受理(受付)してもらえません。
自分や知り合いを対象にした捜査や調査が開始されたようだといった情報がどこかから入って不安になったような場合には、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けた方がよいでしょう。身に覚えがないようなことであれば、警察官や検察官に事情を説明して疑いを晴らす必要がありますし、実は心配する必要がないことだと分かれば不安が解消されるからです。
捜査・調査の実情
任意捜査・調査
捜査機関は、被疑者(容疑者)や参考人(目撃者など)の取調べや現場の実況見分等を行い、また証拠物の提出を受けたりして証拠を集めます。調査機関も同様ですが、取調べのことを質問調査といっています。
捜査・調査は、任意つまり相手方の同意や承諾を得て行うのが原則です。強制捜査・調査は、法律に特別の規定がある場合に限り行うことができます。任意捜査・調査の段階では、広く関係者の取調べ等が行われるのが普通です。捜査・調査機関の側でも容疑事実や容疑者を絞り込めていないからですし、初めは参考人として取調べを受けていたのに途中から被疑者(調査の場合は嫌疑者といいます)として扱われることもあります。犯罪の容疑をかけられても任意捜査・調査の段階では取調べに応じる義務はありませんから警察等へ出頭するのを拒否することは可能です。
この段階での弁護士の役割
自分が何の容疑で取調べを受けているのか分からず不安であるとか、こういう容疑で取調べを受けるいわれはないと思う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が捜査・調査機関と交渉したり、意見書を提出したりして、容疑があらぬ方向に広がったり、依頼者が逮捕されるのを防ぐことが期待できます。不安な状態のまま捜査・調査の流れに身を任せるのは決していいことではありません。
一般の人は、そもそも捜査・調査に応じたり、証拠物を提出したりする必要があるかどうかさえ判断に困るのではないでしょうか。例えば、痴漢事件の犯人だといわれて急に逮捕され、その後釈放になり、任意捜査に変わったとしても、起訴されてしまえば、99%以上の確率で有罪になっているのが現実です。本当に痴漢をしていないのなら起訴されないように弁護士の力を借りましょう。
強制捜査・調査
強制捜査(令状を取って相手の同意・承諾がなくても行える捜査・調査)の代表は、逮捕・勾留と捜索・差押え(いわゆるガサ)です。前にも書いたように調査機関には逮捕権限はありません。
逮捕の手続には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕(例えば痴漢だといわれて電車内や駅事務所で逮捕される場合)の3種類があります。ここでは、最も多い通常逮捕手続について説明します。被疑者(容疑者)が犯罪を犯したと思われる相当な理由があるときは、捜査機関は逮捕状を裁判官に請求した上、被疑者を逮捕することができます。警察官が逮捕したときは、留置の必要がなければ釈放し、留置の必要がるときは48時間以内に検察官に送致(いわゆる身柄送検)しなければなりません。検察官は、送検された被疑者に留置の必要がないと認めるときは釈放し、留置の必要があると認めるときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留の請求をしなければなりません。検察官が自ら被疑者を逮捕したときは、留置の必要がないと認めるときは釈放し、留置の必要があると認めるときは、48時間以内に裁判官に勾留の請求をしなければなりません。脱税、金商法違反、独禁法違反、検事が独自に見つけ出した贈収賄事件等は検事が自ら被疑者を逮捕する場合です。被疑者は、逮捕されたとき、犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる(弁護士を頼める)ことを告げられます。弁護士を頼みたいといえば警察や検察官が必要な手続をしてくれますが、予め相談している弁護士がいないと誰が来るか分からないことになります。
検察官は、被疑者が罪を犯したと思われる相当な理由がある場合で、①被疑者に定まった住居がないとき②被疑者が証拠を隠滅する恐れがあるとき③被疑者が逃亡する恐れがあるときのどれかの理由があるときに裁判官に勾留を請求します。一般刑事事件のうちの約3割が逮捕勾留されていると考えられます。裁判官は、勾留の理由がないと認めるとき等を除いてすみやかに勾留状を発布しなければならず、勾留状を発布しないときは釈放を命じなければなりません。勾留が認められると被疑者は警察の留置場や拘置所等に入れられます。勾留の期間は、勾留請求した日から10日間ですが、さらに10日間の勾留延長が認められるのが普通です。
捜査機関は、勾留中に被疑者や参考人の取調べ等を行います。検察官が自ら被疑者を逮捕勾留した場合や裁判員裁判対象事件など重大な事件については取調べの様子を録音録画する取り扱いになっていますが、多くの事件は録音録画の対象外とされています。録音録画されていれば、変な取調べはしずらいのですが、録音録画をしていないと違法・不当な取調べが行われてもそれを証明するのは容易ではありません。裁判官は、検察官の請求によって、被疑者と弁護人以外の者つまり家族や会社の同僚などとの接見(面会等)を禁止することができます。弁護士以外の人とは面会も手紙のやり取りもできなくなり、孤独な留置状態が続くことになります。
最近はメールでのやりとりなどが重要な証拠になるため、逮捕の前にいわゆるガサを先行させ、パソコンや携帯のデータを差押え、メール等の内容を解析してから逮捕・勾留に移行することが多くなっています。
この段階の弁護士の役割
弁護士は、勾留の理由や必要がないと考えるときには、捜査機関や裁判官に面談を求め、その理由を説明して勾留されないよう活動することができます。不幸にも逮捕・勾留されてしまった人は、同じ経験を何度かした人でもない限り、動揺し、今後どうなるのか、自分や家族の将来はどうなってしまうのかなどと考え、不安でいっぱいになりますし、家族の生活費や会社の資金繰りの手配なども必要になることがあります。こんな状態に置かれた人が最も頼りにできるのが弁護士であり、最も重要なのが弁護士との接見(面会)です。被疑者は、弁護士を通じて外の社会との接点を保つことができますし、取調べを受けるに当たっての貴重かつ重要なアドバイスを受けることもできます。強い味方を得ることで折れそうになる気持ちを立て直すことも可能です。しかし、いくら弁護士が付いたからといって、その弁護士が家族や会社との単なる伝言役にすぎないようではあまり意味がありません。刑事事件の実務経験を積み、取調べの実情にも精通した弁護士によるサポートを得たいものです。
弁護士は、被疑者が否認している場合には、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。被疑者が認めている場合には被害者のいる犯罪であれば示談を進めたり、検事に起訴しないよう意見書を提出したりします。勾留に関しては、勾留決定に対する不服申立て(準抗告、勾留取消請求、勾留執行停止の申立て等の対抗手段)もでき、裁判所を説得できるだけの理由があるときは、これらも被疑者を拘禁状態から解放する有効な法的手段となりますが、実務的にはかなり難しいといわざるを得ないのが実情です。
事件の処理
事件の処理を行うのは検察官(検事、副検事)です。事件の処理は、公訴の提起(起訴)と不起訴に分かれます。
起訴
検察の実務では、有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴するという原則があります。しかし、多くの無罪判決が言い渡されたり、再審請求事件で無罪が言い渡されているのを見ると、この原則が厳格に守られているわけでもなさそうです。起訴されると、被疑者から被告人に呼び名が変わります。
起訴にはいくつかの種類があります。
- 公判請求
検察官が公訴を提起し公判を請求する場合です。裁判ドラマ等で見るあの手続きが公開の法廷で行われることになります。なお、検察官は、事案が明白で、軽微であるときは、公訴の提起と同時に書面で即決裁判手続を申し立てることができ、この場合は簡単な公判手続で判決が言い渡されます。
- 略式手続
検察官は、①100万円以下の罰金・科料に当たる事件で②被疑者に略式手続によることについて異議がないときに、簡易裁判所に対し、公訴の提起と同時に略式命令を請求できます。裁判所は、公判を開かず、記録を読んで有罪と認めれば略式命令を発し、その謄本が被告人に送達されると身柄拘束中の被告人は釈放されます。
不起訴
検察官の行う処分のうち公訴を提起しない処分を不起訴処分といいます。不起訴処分にもいくつかの種類がありますが、主なものは次の三つです。
- 起訴猶予
犯罪事実は認められるが、犯罪の軽重・情状等により起訴を必要としないときにする処分をいいます。事件の軽重、被疑者の役割・行為の内容、前科の有無、示談の成否、反省の態度、再犯の可能性等が考慮されます。
- 嫌疑不十分
問題となっている事実につき、犯罪の成立を認定する証拠が不十分なときにする処分です。
- 嫌疑なし
問題となっている事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定する証拠がないことが明白なときにする処分です。
この段階の弁護士の役割
弁護士としては、ここで説明した検察官による処分につき、被疑者が否認している場合には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指して、被疑者に有利な証拠を集めたり、検察官に意見書を提出するなどの弁護活動を行い、公判請求されてしまった場合には、無罪を目指して公判活動を展開することになります。
被疑者が認めている場合には、「起訴猶予」を目指して示談を成立させたり、犯情や情状について意見書・上申書を作成するなどして検察官に提出します。
起訴猶予が困難な場合には、略式請求を目指して活動することになります。犯罪によってはそもそも略式請求ができない事件もあるわけで、その場合は公判請求されても仕方ないことになります。勾留中に公判請求されると被告人の勾留(身柄の拘束)も続くので、保釈請求して拘禁状態から解放してもらう必要があります。否認事件や重大事件の場合、保釈を勝ち取るのは困難な場合が多いのが実情ですが、被告人との打合わせを十分に行うためにも是非とも保釈を勝ち取る必要があり、弁護士の腕の見せ所ということになります。
第一審の裁判手続き
第一審は、起訴状朗読→認否(罪を認めるかどうかの被告人側の意見)→冒頭陳述(検察官が証明しようとする事実の主張)→証拠調べ(証人尋問、供述調書の朗読など)→論告・求刑(検察官の意見)→弁論(弁護人の意見)→判決(裁判官の判断)という流れで進められます。無罪主張をする場合でも刑の重さを争う場合でも、控訴審で新たな証拠調べをしてもらうのは極めて困難であるため、第一審での審理が重要です。裁判員裁判対象事件や複雑・重大事件等の場合には、争点の整理や公判で取調べる証拠を決定するため、公判前整理手続という打合せが行われます。
無罪主張をする場合
証拠調べが最も重要で、検察官が請求した証拠のうち被告人が納得できないものを不同意とする(証拠とすることに反対する)と、証人尋問が行われます。もちろん被告人側も被告人に有利な証人の尋問を請求できます。証拠物の取調べや検証なども行われます。被告人質問(被告人が法廷で、弁護士や検察官、裁判官からの質問に答えること)の内容も証拠になりますから、被告人は主張したいことを十分に述べる必要がありますが、場合によっては黙秘権を行使することもあります。検察官の論告に対し、弁護人は弁論を行い、被告人が無罪であることを説得力を持って主張しなければなりません。
刑の重さを争う場合
検察官の懲役刑・禁錮刑の求刑に対し、罰金刑を求めたり、執行猶予付きの判決を求める公判活動が行われます。事実関係に争いがなければ、検察官の請求証拠を同意し、被告人に有利な証拠、具体的には、情状証人や示談書・嘆願書の取調べをしてもらい、被告人質問でも反省していること等を述べることになります。
この段階での弁護士の役割
刑の重さを争う場合も同じですが、無罪主張をする事件では、弁護士の能力が特に重要です。事件の本質・ポイントを見抜き、効果的な立証を行うためには、経験に裏打ちされた高度な技術・判断能力が必要ですし、被告人にとって有利な証拠を収集する技術・能力も必要です。弁護士は、被告人と十分な打合わせを行い、最良の弁護方針を決定し、それを実行する必要がありますが、ここでも刑事事件についての経験がものをいいます。
弁護士の能力・手腕が不足していたがため、執行猶予が付かずに実刑になったり、無罪が取れずに実刑判決が言い渡され、弁護士が替わって、控訴審でやっと執行猶予が付いたり、無罪になったなどということは、たまにあることです。
控訴審、上告審
一審でせっかく無罪や執行猶予付きの判決を勝ち取っても、検察官が、控訴することがありますので、控訴審での対応が必要になります。控訴審で勝っても検察官が上告すれば、最高裁での対応が必要になります。逆に一審で有罪になったり、実刑判決を言い渡されれば、それを不服として控訴できますし、さらに上告して最高裁まで争うことが可能です。
この段階での弁護士の役割
被告人側が、控訴、上告した場合には、控訴趣意書、上告趣意書というものを作成・提出しなければなりません。検察官が控訴、上告した場合には、被告人側は、答弁書を作成・提出しなければなりません。被告人側が、一審判決や控訴審判決に納得できず、控訴、上告するということは、プロの裁判官の判断が明らかにおかしいと、高等裁判所や最高裁判所の裁判官を説得しなければならないということですから、これらの対応には高度の専門知識や能力が必要とされることが明らかです。
刑事事件の弁護士を選ぶポイント
刑事事件は捜査段階、一審の裁判段階の弁護活動が極めて重要です。そのため、次のような条件を備えた弁護士を選任することをおすすめします。
事件の見通しを立てられること
捜査・調査の段階では、弁護士の情報源は、ほとんど被疑者だけということになります。その限定された情報を元に今後の捜査の方向や結論を見通せなければ、適切なアドバイスや弁護活動をすることはできません。不起訴処分を狙うのか、略式請求を狙うのか等を的確に判断できなけばならないということです。被疑者から「先生、今後どうなりそうでしょうか」と聞かれて、「現状では何ともいえませんね」などと答えるような弁護士に弁護を依頼するのは避けた方がいいでしょう。
公判請求された場合には長期の勾留を覚悟で争うべきなのか、保釈を狙った戦術をとるべきなのか等を的確に判断できなければなりません。延々と争って勾留が続き、結局実刑になったのでは被告人にとっていいことはないということになるでしょう。
事件のポイントを見抜き、それに沿った有効な立証活動ができること
事件のポイントを見誤り、東が主戦場であるのに、西ばかり攻めているようでは、有効な弁護活動はできません。ポイントを絞ってその事件の弱点を鮮明にする立証活動を行う必要があります。
弁護士と打合せをしていた依頼者が、「ポイントはそこじゃないだろう」と思うようであれば、違う弁護士にも相談してみるとよいでしょう。
証拠を集める知識・能力があること
弁護士には捜査機関のような権限はないので、証拠を集めるのは大変ですが、事件のポイントとなるべき証拠を発見できれば事態は大きく変わることになります。そういう証拠を集めることができる知識・技術と能力が求められます。
これは弁護士に「先生どうやって証拠を集めましょうか」と聞いてみれば、知識・能力を確認できると思います。
説得力のある意見書等の文書を書ける、あるいは意見がいえること
捜査段階では検事等に、公判段階では裁判官に「なるほどそういう見方もできるか」「確かにその点は証拠が不十分だな」「検察官の見立ては間違いではないか」と思わせるような文書を書けなければなりません。せっか証拠を集めてもそれを有効に使うためには説得力のある意見を相手に伝えられなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
弁護士と話しをしてみて、依頼者が納得できないようであれば、逆にいえば、依頼者を説得できないようであれば、違う弁護士にも相談してみるとよいでしょう。
刑事事件の弁護士の選び方まとめ
上記ポイントをまとめれば、刑事事件の弁護士には、見通しを誤らず、事件の本質・ポイントを見抜き、効果的な立証を行い、相手を説得する能力が求められるということになります。刑事事件に多く関わり、経験を積まないとなかなかこれらを身につけることは、困難だと思われます。しかし、経験がなくとも意欲と能力がある優秀な弁護士であれば適切な弁護活動を行うことも可能だと思われますので、信頼するに足りる弁護士かどうかを上記1から4をヒントに見極めてください。もちろん、弁護士の要求する報酬額が、適正・妥当なものであることも重要です。


 逮捕後に勾留される場合とその対応方法
逮捕後に勾留される場合とその対応方法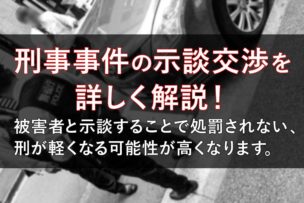 刑事事件を示談で解決する方法、示談交渉から示談書の作成、示談金相場まで。
刑事事件を示談で解決する方法、示談交渉から示談書の作成、示談金相場まで。 不起訴とは?前科がつくの?不起訴と起訴猶予・無罪の違いを解説
不起訴とは?前科がつくの?不起訴と起訴猶予・無罪の違いを解説