
全ての遺産を他の相続人や第三者に譲渡する旨の遺言があった場合等、期待していた相続分がなくなってしまうというケースがあります。このようなケースでは、法律上,遺留分という権利が認められている人(以下「遺留分権利者」といいます)であれば,遺留分減殺請求という制度により、ある程度の遺産を確保することができます。泣き寝入りすることなく、遺留分に相当する取り分を取り戻すために、以下、遺留分減殺請求をするために知っておきたいポイントを解説します。
遺留分とは何か
遺留分の意味
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)です。これは、遺言によっても自由に変更することができないものです。したがって、遺留分権利者に該当するのであれば、遺言で自分の相続分はないものとされていたとしても、遺産を相続することとされた他の相続人や第三者に対して、遺留分に相当する財産を返すよう請求することができるのです。
誰が遺留分権利者になるのか
法律上、遺留分権利者となるのは、被相続人の
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母等
とされています。
兄弟姉妹については、相続人となる場合でも遺留分はありません
また、子が先に死亡していた場合には、その直系卑属(子や孫)も遺留分権利者となります。
遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は少し複雑です。
まず、遺留分権利者の全体に残される分を計算します。これを「総体的遺留分」といいます。
次に、総体的遺留分に、個々の相続人の法定相続分の割合を掛けることで、自分の取り分が算出されます。これを「個別的遺留分」といいます。
整理すると、次の計算式のとおりとなります。
個別的遺留分の額=遺産の総額×総体的遺留分の割合×法定相続分の割合
遺留分の計算がややこしいのは、上記の総体的遺留分が、誰が相続人となるかによって異なるからです。法律上、直系尊属のみが相続員である場合には、被相続人の財産の3分の1が総体的遺留分となります。それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が総体的遺留分となります。
具体的な事例を通して、個別的遺留分がどのように算出されるか確認してみましょう。
【事例1】
- 遺産の総額:1,200万円
- 相続人:父と母のみ
- 遺言の内容:第三者に全財産を相続させる
このケースでは、父と母が、遺留分権利者として、第三者に対し返還請求をします。
直系尊属のみが相続人となりますので、総体的遺留分の額は次の通りになります。
1,200万円×1/3=400万円
さらに、相続人が父と母の場合、法定相続分はいずれも1/2ずつなので、父と母それぞれの個別的遺留分の額は次の通りになります。
400万円×1/2=200万円
このケースでは、父と母は、それぞれ、200万円の限度で、遺産を相続した第三者に返還を求めることができるということになります。
【事例2】
- 遺産の総額:1,200万円
- 相続人:妻と長男・次男
- 遺言の内容:長男に全財産を相続させる
このケースでは、妻と次男が、遺言で全財産を相続することになった長男に対し返還請求をします。
相続人は配偶者と子なので、総体的遺留分の額は次の通りになります。
1200万円×1/2=600万円
さらに、配偶者である妻の法定相続分は1/2、子が2名なので、次男の法定相続分は1/4となり、妻の個別的遺留分の額は、次の通りになります。
600万円×1/2=300万円
次男の個別的遺留分の額は、次の通りになります。
600万円×1/4=150万円
このケースでは、妻は300万円、次男は150万円の限度で、長男に返還を求めることができるということになります。
遺留分は放棄できるのか
これまで解説したとおり、遺留分は、遺言によっても被相続人が減らしたり無くしたりすることができないものですが、遺留分権利者が自ら放棄することはできるのでしょうか。
法律上、相続の開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要とされています。逆に、相続の開始後であれば、自由に放棄ができることになります。例えば、会社のオーナーが長男に後を継いでもらいたいが、他にめぼしい財産がない、という場合などに、他の相続人に遺留分を放棄してもらえるかが問題になります。
ちなみに、相続人の1人が遺留分を放棄した場合でも、その分他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求権はいつ時効になるのか
法律上の権利の多くは、使わずに放っておくと時効となり消滅してしまいます。遺留分減殺請求権についても、法律上時効が定められており、しかも、時効となる期間は1年と短いため、注意が必要です。
では、どの時点から1年がカウントされるのでしょうか。
これは、法律上、遺留分権利者が、相続が開始されたことと、遺留分減殺請求の対象となる行為があったことの両方を知った時点からとされています。したがって、相続開始からは1年が経っていても、遺留分を侵害するような内容の遺言があることを知らなければ、時効にはならないということになります。ただし、法律上、遺留分権利者の認識とは関係なく、相続開始の時点から10年経った場合にも時効となりますので、この点も注意が必要です。
時効とされないための注意点
このように、遺留分減殺請求権の時効期間はとても短いため、遺留分権利者にとって、時効とならないようにする手当は極めて重要です。
では、どうすれば時効にならないのでしょうか。
判例上、遺留分返還請求権を行使する旨の意思表示を相手方にすれば、時効にはならないとされています。この意思表示の方法は特に制限はされておらず、口頭で行ってもよいのですが、証拠を残しておかないと、後で争いになった場合に不利になってしまいます。
そこで、証拠を残すために最も確実な方法として、内容証明郵便を相手方に郵送することが推奨されます。実際、遺留分減殺請求を弁護士に依頼した場合には、まず最初に相手方に対して内容証明郵便により返還請求を行うのが通常です。内容証明郵便による請求は、慣れていないと手間がかかり、費用も2000円前後かかってしまいますが、後に相手方から時効を主張されて争われるリスクを考えると、ぜひとも確実に行っておきたいところです。
遺留分減殺請求をするとどうなるか

遺留分減殺請求の効果
遺留分減殺請求権を行使すると、対象となった贈与などの行為は、遺留分を侵害する限度で失効するとされています。そうすると、現預金については、遺留分に相当する金額を相手方に対し請求をすることができます。これに対し、不動産等の財産については、相手方と共有となります。
しかしながら、請求を受けた相手方が、素直に返還に応じてくれることはあまり期待できませんし、また、不動産についても共有状態では利用することも売ることもできず不都合です。単に遺留分減殺請求をしただけでは、何の解決にもならないのが実情です。
実際の解決方法
そこで、実際には、相手方と協議し、遺留分に相当する金額を返還してもらうことになります。また、相手方との間で、遺留分に相当する金額に争いが生じるなど協議による解決が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
実際に遺留分減殺請求を行い、遺留分に相当する金銭の返還を受けるまでの手続きや注意点等については、下記ページをご確認ください。
まとめ
遺言の内容に納得のできない相続人の方は、遺留分減殺請求をすることを検討し、時効とならないうちに相手方に内容証明郵便を郵送しましょう。遺留分減殺請求の時効の項でも解説したとおり、遺留分減殺請求権の時効期間は1年と極めて短いため、権利の実現のためには、まず、証拠に残るかたちで請求の意思表示をすることが肝要です。その上で、相手方が素直に応じないなど、財産の取戻しが難しそうであれば、専門家である弁護士に調停等の手続きを依頼することをおすすめします。


 遺留分減殺請求の流れと手続きにかかる費用
遺留分減殺請求の流れと手続きにかかる費用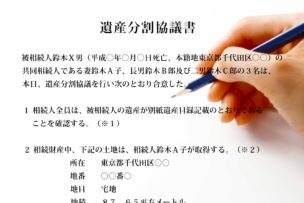 遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法・サンプル文例
遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法・サンプル文例 遺産分割を弁護士に相談する3つメリットと弁護士の選び方のポイント
遺産分割を弁護士に相談する3つメリットと弁護士の選び方のポイント 遺産分割にかかる費用を詳細解説!気になる弁護士費用はいくら?
遺産分割にかかる費用を詳細解説!気になる弁護士費用はいくら? 遺産分割調停の申立てから解決までの流れを徹底解説!必要書類や管轄は?
遺産分割調停の申立てから解決までの流れを徹底解説!必要書類や管轄は?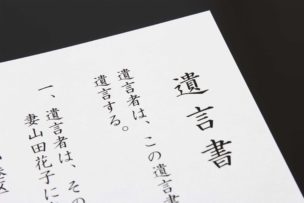 遺言書の種類は3つ!遺言書の書き方をサンプル文例とともに解説
遺言書の種類は3つ!遺言書の書き方をサンプル文例とともに解説 公正証書遺言の作り方〜費用(手数料)や必要書類を徹底解説!
公正証書遺言の作り方〜費用(手数料)や必要書類を徹底解説! 相続放棄の注意点、借金を相続しないために知っておきたい相続放棄のすべて
相続放棄の注意点、借金を相続しないために知っておきたい相続放棄のすべて